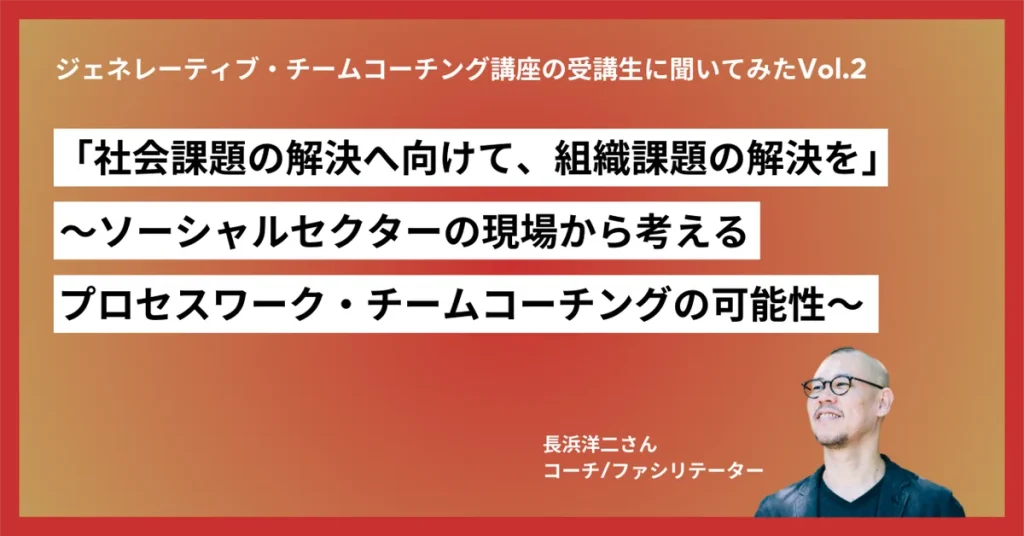社会課題の解決に向けて、組織課題の解決を
アーノルド・ミンデル博士が創始した「プロセスワーク」を応用し、組織やチームの変容を実現するリーダーやファシリテーター、コーチを育成する、「ジェネレーティブ・チームコーチング講座(GTC)」(主催:組織開発コーチ協会)を修了しました。
プロセスワークは、ユング派の分析家アーノルド・ミンデル博士が1970年代に提唱した心理学的アプローチであり、個人や組織が抱える問題や葛藤を、変化の兆しとして捉え、深い気づきを通じて変容を促す手法です。その実践には、夢分析、身体感覚の探求、対話、ロールプレイなどが含まれ、個人の成長や組織の発展に向け、心理療法、コーチング、組織開発、紛争解決など、さまざまな分野で活用されています。
GTCはこのプロセスワークをベースに、チームや集団に変化を起こすためのコーチングスキルを学ぶプログラムで、人と人の関係やグループの中で起きる深い心の動きや力の流れに注目します。チームの中では、立場や意見、価値観の違いなどから対立やすれ違いが起こりますが、それを乗り越えてチームが一つにまとまるための方法を学びます。人が集まると、個人だけでは生まれない独特のパターンや流れができることがあるため、チーム全体の流れに意識を向けて働きかけることで、チームの行動や成果を大きく変えることができます。そのためにプロセスワークの知恵を使いながら、組織づくりやマネジメントに関わる人が、チームの力を引き出すコーチングの技術を身につけることを目的としています。
自分は、NPOやNGOをはじめとするソーシャルセクターにおいて事業のコンサルティングや個人向け&チーム向けのコーチング、様々な場づくりのファシリテーションを行なっていますが、この度、「社会課題の解決に向けて、組織課題を〜ソーシャルセクターの現場から考えるプロセスワーク・チームコーチングの可能性〜」と題して修了生向けのインタビューを受ける機会をいただきました。ソーシャルセクターにおける実践の現場からという視点で、GTC受講の背景や目的などについてお話ししましたので、以下、要旨をお伝えします。
<インタビュー記事まとめ>
1. 集団の対立や葛藤に介入する実践的なチームコーチングを学ぶ
チーム内の意見の対立や関係のもつれなど、葛藤が起きたときに、安心・安全な場を保ちつつ介入し、対話と変化を促すチームコーチングの技術を学ぶ。表面的な調整ではなく、深層にある力学を扱う実践力を育てる。
2. チームの微細なシグナルをキャッチし、変化を見立てるスキル
表情、沈黙、場の雰囲気など、言葉にならない微細なシグナルに気づく力を高め、チームの変化の兆しを読み解く力を身につける。こうした観察力が、チームの成長のタイミングを見極める鍵になる。
3. 日常や会議・ミーティングでも活かせるチームコーチング
会議やミーティング、日常のコミュニケーションの中でも使えるコーチングの視点と手法を学ぶ。特別な場面だけでなく、日々の仕事や関係づくりのなかでチームの力を引き出す関わり方を習得する。
4. ソーシャルセクターこそプロセスワークが活きる
NPOや行政など多様な立場が関わるソーシャルセクターでは、見えにくい力関係や価値観の違いが複雑に絡み合う。こうした場でこそ、プロセスワークのアプローチが対話と協働を進める力になる。
5. 社会課題の解決に向けて、組織課題の解決を
社会課題に取り組むには、まず自分たちの組織が健全であることが大切。この講座では、チームや組織の課題に向き合い、関係性の質を高めることで、社会全体への変化を促す視点と技術を学ぶ。
このようなコーチング手法に興味をお持ちの方は、ぜひ一度、コーチングを体験してみることをお勧めします。昨今、ソーシャルセクターでも代表者がコーチングを受けたり、福利厚生の一環としてスタッフがコーチングを受ける機会が提供されるケースも出てきました。そうした個人にとどまらず、さらに集団やチーム、組織、さらには地域の課題解決に向けた新たな手法としてご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。
個人・チームに対する各種コーチングの相談/依頼 → https://mojo.co.jp/contact/